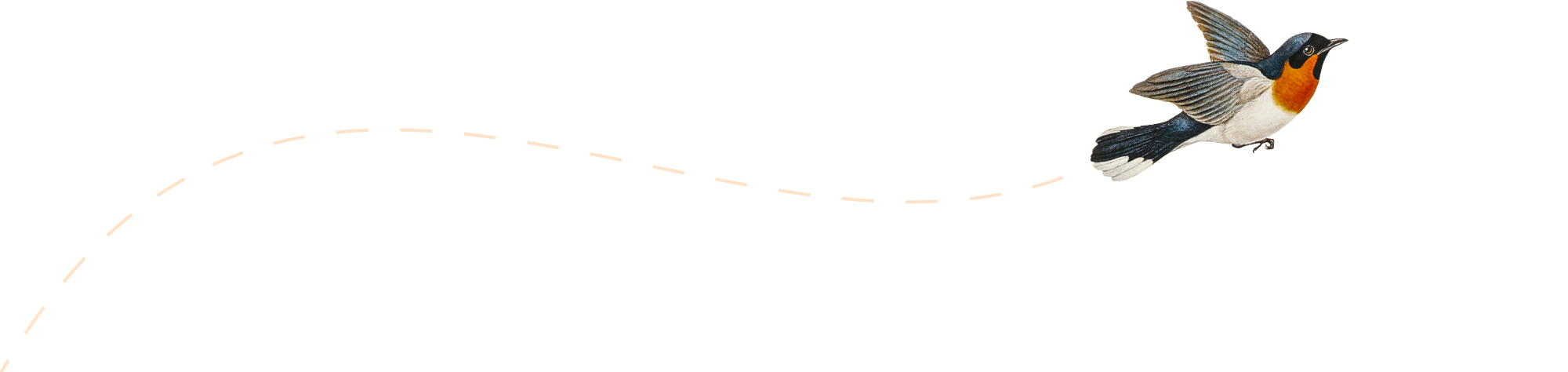-
장재형목사 HBS 회장 |성경 보급에 집중하여 복음을 효과적으로 전하자
홀리바이블소사이어티(HBS)는 최근 이슬람 선교를 위한 노력으로 아랍어권 서비스를 도입하면서 큰 주목을 받고 있다. 이 단체의 회장으로는 한국인 장재형목사가 선임되어 활동 중이다. HBS는 국제적인 성경 보급 단체로서, 디지털 기술과 인터넷을 활용하여 모든 사람들이 성경에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 설립되었다. 장재형목사는 선교사를 파송할 때 언급하며, 성경이 아직 인쇄되지 않거나 정부에 의해 금지된 국가들에서도 복음을…
-
장재형목사, 사랑의 하나님과 거룩의 하나님, 그리고 하나님 나라의 비밀
장재형목사(Olivet University Founder)는 한국교회 안에서 종종 분리되어 다루어지는 “사랑”과 “거룩”을 하나의 통전적 진리로 결합시키는 설교자다. 그는 주기도문—“하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하시오며…”—을 통해 하나님의 초월성과 임재, 삼위일체와 성육신, 기도의 본질, 인간 실존의 목적을 밀도 있게 조명한다. 그가 말하는 사랑의 하나님은 인격과 인격의 친밀한 만남, 곧 “얼굴과 얼굴을 맞대는” 관계로 드러나며, 이는…
-
장재형목사 고린도후서 9장 해설
고린도후서 9장은 흔히 ‘연보’로 요약되지만, 자세히 들여다보면 은혜가 어떻게 인간의 마음을 넉넉하게 만들고, 그 넉넉함이 이웃을 살리는 나눔으로 흐르며, 그 나눔이 다시 하나님께 넘치는 감사로 되돌아오는 거대한 순환의 서사를 정교하게 그려낸다. 장재형(장다윗)목사는 이 장을 읽을 때 무엇보다 먼저 복음이 추상적 표어가 아니라 구체적 사랑의 형태를 띠는 순간에 비로소 진실해진다는 사실을 환기한다. 기근으로 지쳐 있던 예루살렘 교회를 돕는 이방 교회들의 연보는 단지 물질의…
-
장재형 목사 ‘성전을 헐라’—요한복음 2장으로 읽는 새 성전과 영적 개혁
장재형(장다윗)목사는 “성전을 헐라”는 예수의 급진적 선언을 요한복음의 핵심 축으로 붙들고, 오늘의 교회가 무엇을 허물고 무엇 위에 다시 세워야 하는지 해설한다. 많은 이들이 이 구절을 예루살렘 성전의 파괴 예언으로만 이해하지만, 그는 이를 타락한 종교 구조와 인간 중심 신앙을 뿌리째 흔드는 영적 개혁의 외침으로 본다. 요한복음 2장에서 예수는 성전 뜰의 상인들과 환전상들을 내쫓으며 “내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라”고 선포했고, 이어 “이 성전을 헐라 내가…
-
David Jang – Romains 9 et le « reste »
1. Au-delà de la sotériologie, vers l’eschatologie Le chapitre 9 de l’Épître aux Romains occupe une place cruciale en ce qu’il aborde de manière approfondie, aux côtés de la christologie (qui est Christ ?) et de la sotériologie (comment le pécheur est-il justifié et parvient-il au salut ?), la dimension eschatologique (où va l’Histoire, comment…
-
张大卫牧师——罗马书第九章与“余民”
1. 超越救恩论,进入末世论 罗马书第九章在基督论(基督是谁)、救恩论(罪人如何被称义而得救)之外,也正式深入探讨末世论(历史将如何流向终局,基督徒在最后时刻应当如何生活),因此在整卷书中占据着非常重要的分水岭地位。张大卫牧师在解读罗马书第九章时强调,从这里一直到第十一章的经文,不仅仅是学术性的圣经诠释,更是实质上告诉我们“已经得救的人应当如何活出信仰”的具体而真实的信息。对基督徒来说,罗马书第一到第八章已经揭示了救恩论的核心,“唯独恩典、唯独信心、唯独圣经”(宗教改革的口号)反复被强调,教导我们只有通过耶稣基督的赎罪大工才能得到救恩,这一点已经非常清楚。然而,救恩并非结束;得救之人如何在神主权的带领下,在历史终结的进程中承担责任与角色,这才是末世论真正关注的焦点,也是罗马书第九章到第十一章的精髓所在。 张大卫牧师指出,贯穿罗马书的一大主题便是“神在人类救恩历史中,究竟通过怎样的路径展开祂的作为”。正如旧约圣经已经显明,神要拯救在罪中的人类,首先拣选了“选民”——以色列,并赐给他们话语、敬拜的体系和圣洁的礼仪,好让救赎主最终在他们中间诞生。然而,纵观历史,以色列常常堕落、败坏,未能完全遵行神的旨意。即便如此,圣经多次强调,神从未停止祂的救恩计划,而是必定借着“余民(remnant)”来延续救恩的工作。罗马书第九章所提出的“余民的教义”,正是告诉基督徒在历史的末后时代与混乱之中,应当如何坚立的极其要紧的洞见。 在这一点上,张大卫牧师强调,没有正确的末世论视野,而只是一味强调基督论和救恩论,可能会失去信仰的重要平衡。因为基督信仰不仅仅是“耶稣是谁”这一知识性的理解,或“我如何成为天国子民”之救恩论的确据,而是必须包括“已经得救之人,如何参与并活在神的救恩历史当中”这一末世观与历史观。所有人都注定在有生之年走向终点,但历史在神的主权之下仍在向前流动;即便在这一过程中,个人会软弱、教会会混乱,但神总是保留了“余民”以延续救恩的谱系。 张大卫牧师强调,“余民”这一概念不仅存在于以色列的历史中,更是关乎整个教会史理解的关键。无论是初代教会在逼迫中守住宝血的见证,中世纪的黑暗中依然有“看不见的教会”坚守正统信仰,还是宗教改革时期那些以“唯独耶稣、唯独信心、唯独圣经”为口号、甘愿殉道的改革者,背后都能看见“神所保留的余民”的身影。正是透过这些“余民”,历史不断向前推进,直到耶稣基督将在末了再临、完全恢复神的统治之日的到来。 罗马书在这样的脉络中,特别在第九章到第十一章,深入探讨了“以色列与新的以色列”这一主题:神如何拣选了以色列,但他们之中多数人却未接受弥赛亚,于是福音之门向外邦人打开。末了,以色列要得着恢复的应许也被提及。保罗由此论述“谁才是真正的以色列人”?答案并非仅仅在于血统,而是那些相信并持守神应许的人才是“真以色列人”,而历史的下一个阶段正是透过这些人来承接。这里“余民”这一概念便是核心:尽管多人会离弃信仰、向世界妥协,但仍会有一群人继续顺服神的话语、承认耶稣基督为主,并坚持福音到底。 基于此,马太福音24章、马可福音13章、路加福音17章所记载的“小启示录”(Little Apocalypse)里,耶稣所说“惟有忍耐到底的,必然得救”的教导,也与罗马书第九章紧密相连。耶稣预言末世来临之际,假先知会出现,罪恶会横行,爱心会冷淡,这些迹象在初代教会已经部分应验,如今依旧如此,并将在最后变本加厉。尽管如此,张大卫牧师指出,耶稣的警示并非要使我们惧怕,而是要为我们带来“在末了如何坚持信心、继续承担神的救恩使命”的勇气与盼望。在这里,“余民”这一主题与耶稣“忍耐到底者得救”的话语交织成强大的动力。 保罗在罗马书里直接引用了先知以赛亚的话:以色列的子孙虽多如海沙,得救的却只是“余数”;而这一“余数”之所以得以存留,完全是因为神的恩典而不是人自己的功劳。这在救恩论与末世论的层面都是核心真理。我们在基督里之所以能得赦免、称义,百分之百是因着神的恩典;同样地,越临近末世,越会面临严峻的挑战与攻击,若想坚守信心,也绝不是凭人自己的意志力,而是因神自己在历史中保留人、以恩典扶持他们,最终完成救恩的计划。 张大卫牧师在此特别指出,“余民”教会或个人所肩负的使命,不只是关乎自身的得救,而是一个“保存并让救恩的种子生根发芽”的积极而动态的过程。就像旧约中收割玉米的农夫,哪怕再饥饿,也绝不能把留作来年播种的种子都吃掉;“余民”的含义就在于此。无论历史多么黑暗,教会看似多么堕落,神依然会留下种子,并从那里开启新的历史。这与以利亚在与巴力先知的属灵争战中筋疲力尽、几乎陷入绝望时,神对他说“我却为自己留下七千人,是未曾向巴力屈膝的”(列王纪上19章18节)一事如出一辙。张大卫牧师强调,这一原则在当今教会同样适用。 在末世论视角下,“余民”并非采取逃避或躲藏的消极态度,反而是踊跃参与到神旨意要完成的普世宣教事业之中。耶稣在马太福音24章14节清楚地说:“这天国的福音要传遍天下,对万民作见证,然后末期才来到。”也就是说,当世界逐渐走向审判之时,教会反而必须更加尽力传扬福音、担负宣教使命。而在此过程中,“余民”与“不肯坚持到底的人”就自然地分化开来。“惟有忍耐到底的,必然得救”这句话,也带着祝福应许,那就是:为要完成把福音传给地上各族、各民的大使命,而不疲倦、不停滞、一直跑到终点的那一群人,必将得着救恩的应许。 基于这样的脉络,张大卫牧师清楚提出,面对末世的召命,教会应该如何预备并被建造。他尤其看重“橄榄山讲论(Olivet Discourse)”——即马太福音24~25章、马可福音13章、路加福音21章中耶稣末后的末世信息,并将“奥利韦特(Olivet)”之名用于自己的事工群体和教育机构。这是因为耶稣在橄榄山(Olivet)上所教导的末世迹象、世界结局以及信徒当如何警醒,正是教会与信徒最根本、最具终极性的指令。罗马书第九章所启示的“余民”精神,正与橄榄山讲论之核心交织在一起,教导教会在末世当如何站立得稳。 如果救恩论立场不稳,末世论也必然会出现偏差;若在救恩论中淡化了基督恩典与宝血的价值,末世论就会发展成异端式的末世观,或充斥人的功德、诡计的畸形模式。反之,若一个人已经清晰把握了“我们是完全靠着十字架的宝血而得救”的真理,那么在末世论上,他就会更加注重“余民精神”,既守护恩典,也向世人传扬福音,以动态的方式与神的工作同工。张大卫牧师在研读罗马书第九章与第十一章时,一再强调要抓住“神在末世仍然保留的这粒种子,必将开启新的历史”的应许。无论当下教会和社会多么混乱,教会里必定会有犹如“玉米种子”般的信徒,他们会守住福音的纯正,并为神的国度献身,成为神所留下的“余民”。 罗马书第九章后半段的重点在于:“以色列的子孙虽多如海沙,得救的却是剩下的余民”,而这“余民”正是“按着神的恩典所拣选、归给神的人”(罗马书11章5节)。如同我们本是因恩典得救,在末了也须凭着恩典坚守,让福音得以传扬,并以圣洁的生活成为世上的光,这便是末世之教会应有的态度。张大卫牧师长期以来透过讲道和著述反复强调此观点:当基督论和救恩论已经打好牢固根基之后,就必须正确理解末世论并实践出来;这与罗马书第九章到第十一章的整体脉络一脉相通。 2. “余民”的身份与使命 那么,具体来说,作为“余民”而活的信徒,应当秉持怎样的生活态度与信仰立场?张大卫牧师从两个层面加以归纳:第一,“余民”必须对自己的身份有清晰的认知;第二,“余民”必须守护救恩的种子,并传递给下一代与万国万民。这两者正是末世之教会的重要支柱,也与罗马书第九章和第十一章的教导完全一致。 首先,对自己身份的清楚认知,意味着“我们是因恩典被拣选的,是为神的救恩计划而被留下的”。这绝不意味着自满或骄傲;保罗在罗马书第九章与第十一章里多次强调,这种拣选基于神的怜悯与恩慈,而不是人的行为。换言之,“我之所以成为余民,并非我多么优秀,而是因神的恩典才得以存留。”因此,拥有“余民”身份的信徒也应当极其谦卑,并时刻警惕“任何人若离开恩典,都可能陨落”。 张大卫牧师谈及当代教会所面临的各种混乱,比如教会领袖的道德失败、神学上的分裂,或传统宗派与改革运动之间的冲突。他认为,只有“被恩典抓住并确实站立在真福音中的人”,才会在终局存留下来。而这种“存留下来”并不是透过论断或攻击他人来排除异己,而是通过回归神的话语与福音的大能,在灵里自然显明出谁真正持守了福音、相信十字架和复活的大能,并且忍耐到底,不停传扬并活出福音与爱心。就这样,“余民”与非“余民”便逐渐分辨出来。 清楚的身份认知也意味着基督徒对神圣使命的自觉。“余民”的意义不只是“我已得救”的安心,更是对教会与世界负有重任。我们并不是只为某一代出现而后消失的人,而是承载着要把“圣洁的种子”传递给下一代、以及万国万民的呼召。保罗在罗马书第九、十、十一章的论述中,借以色列为例,不住地呼喊:“未曾听见福音的,怎么能信?没有信心的,又如何得救?”(罗马书10章14节以下),从而极力强调“余民”传福音的使命何等急迫、何等关键。 其次,“余民”必须守护救恩的种子,并传递给下一代与列国。许多人对末世论存在误解,以为“既然末日快到了,我们只要自己坚守信心、躲起来就行”,这是一种逃避主义或宿命论。然而,仔细研读耶稣的教导与保罗的书信会发现,无论如何,教会都不能放弃或停止在世间见证福音的使命。传扬福音、属灵觉醒以及爱心行动在末世更加不可或缺。正因末世临近,教会的责任反而更加沉重:要将福音的种子保存并传播给万国万邦。 在张大卫牧师的牧会与宣教经历中,他曾走遍世界许多地方,看见不少“圣洁的种子”在极度艰难的处境中依旧得以保存与传递。无论是在共产政权国家、伊斯兰地区,或各处饱受宗教迫害的区域,都有地下教会或小型信仰团体不惜冒着生命危险聚会敬拜,并传扬福音。他们就如旧约的“余民”,如新约时代初期的教会信徒一样,正是罗马书所说“因着恩典被拣选”的人。他们没有显赫的教势或丰厚的物质资源,但却完全依靠“耶稣的宝血与神的话语”,坚守信仰。张大卫牧师称此为守护种子的典型榜样。 守护种子并不只是个人的信仰宣誓,也包括教会共同体的敬拜、圣餐、施洗,以及宣教与教导事工,这些都是保有与传递福音种子的途径。张大卫牧师尤其提到教育机构——例如神学院或基督教大学——在培养“余民”和将福音种子传递给下一代方面居于中枢地位。他以“奥利韦特(Olivet)”之名创办了多所教育机构、神学院与大学,正是为了突出“要把主在橄榄山末世讲论(Olivet Discourse)所启示的真理,传授并付诸实践”的神学教育。如今的时代极易被世俗文化与知识冲击而失去神学的本质,需要透过“回到圣经”的教育来兴起“余民”。 张大卫牧师多次强调,“余民”最终会拯救历史。《创世记》中所载,若所多玛和蛾摩拉城中能有十个义人,也可免遭灭亡;这就显示神不是要推进毁灭,而是若能找到追求公义的人,便通过他们开辟救恩之路。以色列历史多次走到崩溃边缘时,都因“余民”而再度有复兴与恢复的起点。在新约的教会史上亦然:许多地区总有被留下的信徒坚守福音,在中世纪的黑暗中也有一把微弱的火炬不曾熄灭,推动后来宗教改革者的兴起。 罗马书第九章就呼应了此一事实:无论当前处境多么黯淡,神主导的救恩大戏绝不会终止;“若不是万军之主给我们存留余种,我们早就像所多玛、蛾摩拉的样子了”(罗马书9章29节)。张大卫牧师将这句话应用在现代:再糟糕的教会现况中,也依旧存在“余民”;神必通过这些人使教会重新站立,并将福音传向全世界。 值得注意的是,“余民”并不会自我封闭在小圈子里沾沾自喜;他们的使命必定是向“拯救世界”的方向展开。因为神在历史中召唤教会,从来不只是为了教会本身,而是嘱咐“你们要作世上的光和盐”。正是在践行光与盐的过程中,末世更大的逼迫与试炼会临到“余民”。对此,张大卫牧师解释说,“能够在此使命中不退缩、不妥协的人,必能忍耐到底,而他们的坚守本身,就成为神拯救、恢复世界的途径之一。” 罗马书第九章27-29节指出,以色列的子孙虽多如海沙,但仅有“余民”得救;也正因这“余民”的缘故,那原本有可能沦为所多玛、蛾摩拉的历史,才获得了新的转机。今天的教会同样如此——这段话不只是一段古老记载,也包含末世性的展望,对教会与信徒既是警示,也带来安慰与盼望。正如张大卫牧师常提醒的,救恩论若越坚固,末世论就越健全;末世论越明晰,教会的身份与使命也越发明确。我们当谨记自己是“按着神的拣选、因恩典而成为的余民”(罗马书11章5节),同时也要成为恩典的管道,向世界撒播福音的种子、践行爱心,并在末后艰难中坚守信心。 整个过程中,历史会在神预定的轨道上不断向目标推进。一代过去,一代又来,大地仍旧存在;而在这大地之上,还有将要得救的人群,以及要把救恩种子传递下去的人。我们受召成为其中的一部分,完全不是靠自己的力量,而是出自神的恩典。所以,张大卫牧师指出,“余民的身份”对末世时代的教会与信徒而言,是至关重要的讯息之一。当我们在救恩论上确据无疑,又能抓住末世论异象,就能在原本可能沦为所多玛、蛾摩拉的世界里,成为开创新历史与复兴之路的“圣洁种子”。为此,我们每天都当儆醒预备,满怀对恩典的感恩,也满怀对世界的怜悯与爱,正如罗马书第九章到第十一章所贯穿的主线般,继续在神的呼召下勇往直前。这正是张大卫牧师不断劝勉信徒的核心教导。 www.davidjang.org
-
張ダビデ牧師 – ローマ書9章と残された者
1. 救済論を超えて終末論へ ローマ書9章は、キリスト論(キリストとは何者か)や救済論(罪人がいかに義とされ、救いに至るか)と並んで、終末論(歴史はどこへ向かうのか、キリスト者は最後にどのように生きるべきか)を本格的に扱う分岐点として非常に重要な位置を占めている。特に、張ダビデ牧師はこのローマ書9章を解説する中で、9章から11章まで続く本文が単なる学問的な聖書解釈ではなく、「救われた者たちが具体的にどのように生きるべきか」を示す、具体的かつ実際的なメッセージであると強調する。 キリスト者はすでにローマ書1章から8章に至る救済論の核心を受け取り、「ただ恵みにより、ただ信仰によって、ただ聖書によって(Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura)」という宗教改革のモットーが繰り返し強調されるように、イエス・キリストの贖いの働きを通してのみ救いが成就する事実を明瞭に知るようになる。しかしそれで終わるのではなく、救われた者がこの歴史の終末と神の主権的な導きの中で、いかなる責任と役割を担って生きるべきか――これこそが終末論の本質的関心事であり、ローマ書9章から11章に込められた核心でもある。 張ダビデ牧師は、ローマ書を貫く大きなテーマの一つとして「神の人類救済史が具体的にどのような経路を通じて展開されるか」を挙げる。旧約聖書ですでに明らかなように、神は罪の中にあった人類を救うため、まず「選民」を選び、その民に御言葉と礼拝体系、聖なる儀式を与え、やがてその民の中から一人の贖い主が生まれるよう摂理してこられた。しかし歴史を振り返ると、イスラエルは腐敗や堕落に陥り、神の御旨に完全には従いきれないことが多かった。にもかかわらず神は決して救いの御業を止めることなく、必ず「残された者(remnant)」を通してその救済史を継続される、と聖書は強調する。ローマ書9章が語る「残された者の教理」は、キリスト者が歴史の最後の時や混乱のただ中でいかに立つべきかを示す極めて重要な洞察である。 この点で、張ダビデ牧師は「正しい終末論の視点を持たずにキリスト論や救済論ばかりを強調することは、信仰の大きなバランスを失う危険がある」と語る。なぜならキリスト教の信仰は、単に「イエスがどのようなお方か」という知的理解や、「私はいかにして天国の民となるか」という救済論的確信にとどまらず、「そのように救われた者が、今やいかに神の救済史に参与して生きるか」という歴史的かつ終末論的な視点が不可欠だからである。人間は皆、有限な存在として地上の生涯を終えるが、歴史は神の主権の内に続いていく。救われた一人ひとりが途中で落胆したり誤ったり、教会が混乱に陥ることはあっても、神は必ず残しておいた群れ、すなわち「残された者」を通して救いの系譜を継承される。 張ダビデ牧師は、この「残された者」という概念がイスラエルの歴史にだけ見られるのではなく、教会の歴史全体を見通す重要なキーワードだと説く。初代教会が迫害の中でも血潮の証しを守り抜いたことも、中世の種々の堕落の中にあっても正統信仰を守り抜いた「見えざる教会」があったことも、そして宗教改革期に「ただイエス、ただ信仰、ただ聖書」を宣言し、殉教もいとわなかった改革者たちがいたのも、すべて「神が残しておかれた者たち」が存在したからだというのである。このように「残された者」を通して歴史は絶えず進展し、ついには地上に再臨されるイエス・キリストと共に、神の完全な支配が回復される日が近づいていく。 ローマ書はこうした流れの中で、特に9章から11章にかけて「イスラエルと新しいイスラエル」というテーマを深く掘り下げている。神がイスラエルを選ばれたが、結局その多くがメシアを受け入れなかったことで、その福音が異邦人へと拡張されていく過程が説明される。そして終末にイスラエルが回復されるという約束にも言及している。パウロはこれを通じて「真のイスラエル」とは誰かを語る。血統的イスラエルではなく、神の約束を信じてすがる者こそが真のイスラエルであり、そのような人々を通して歴史は次の段階へ受け継がれていく。ここで中心的となるのが「残された者」の概念である。多くの者が背教したり妥協したり、世の価値観に屈服したりする中でも、終わりまで神の御言葉に従順し、イエス・キリストを主と告白し、福音を握りしめる者たちが存在する。 この意味で、マタイ24章・マルコ13章・ルカ17章に記されている「小黙示録(Little Apocalypse)」と呼ばれるイエスの言葉、すなわち「最後まで耐え忍ぶ者は救われるであろう」という教えは、ローマ書9章とも密接につながる。終末が近づくにつれ、偽預言者が現れ、罪悪がはびこり、愛が冷えていくというイエスの警告は、すでに初代教会の時代にも部分的に成就し、現代もそうであり、最終的にはさらに深刻化する。しかしそれでも張ダビデ牧師は、イエスのこの教えが私たちを「恐れ」させるためではなく、「いかにして最後まで信仰を守り抜き、神の救いの御業を担うか」に対する勇気と希望を与えるためだと強調する。まさにここでローマ書9章の「残された者」というテーマと、イエスの「最後まで耐え忍ぶ者」という言葉が結びつき、強力なシナジーを生み出す。 パウロはローマ書の中でイザヤの預言を直接引用している。すなわち、イスラエルの子孫の数が海辺の砂のように多くとも、結局は「残された者」だけが救われるという言葉である。このとき「残された者」が持つ重要な特徴は、「人の功績や努力」ではなく「神の恵み」によって保たれ、選ばれている点だ。これは救済論的にも終末論的にも同じ核心である。私たちがキリストにあって罪の赦しと義とを得るのも100%恵みによるように、終末が近づくほど激しさを増す挑戦や攻撃の中で信仰を守ることも、人間の意志や決心だけで可能なわけではない。神が歴史の中で直々に人を残され、その人々を恵みで守られ、ついには救済史を完成されるのである。 張ダビデ牧師は、ここで「残された者」として召された教会や個人の使命は、決して自己の救いにばかり執着するものではなく、歴史の中で神から与えられた「種」を守り、それを育てる積極的かつ躍動的な役割にあると説明する。旧約聖書で農夫がトウモロコシを収穫するとき、どれほど飢えていても、種に使うトウモロコシだけは必ず別にしておく。次の年に蒔く種がなくならないようにするためだ。それこそが「残された者」の意味だというのである。歴史がどれほど暗澹たる様相を見せようとも、教会が世の潮流に押し流され堕落してしまう瞬間があっても、神は必ず種を残され、その種を通して新しい歴史を始められる。この点は、エリヤがバアルの預言者たちとの霊的闘いで疲れ果て、落胆していたときに、神が「バアルに膝をかがめない七千人を残しておいた」(列王記上19:18)と告げられたエピソードと同じだ。そしてこの原理は今日の教会にもそのまま当てはまる、と張ダビデ牧師は強調する。 終末論的な面から見ると、「残された者」とは逃避的で退却的な態度をとる人たちではなく、むしろ世界宣教へと邁進する神の救いの御業に能動的に参加する者たちである。イエスはマタイ24章14節で、「この御国の福音は全世界に宣べ伝えられ、あらゆる国民に対して証しされ、そのときが来るだろう」と語られた。すなわち、世が裁きへ向かう間にも、教会はむしろ福音宣教と宣教の使命を担わなければならず、その過程において残される者とそうでない者が明らかになるというわけだ。「最後まで耐え忍ぶ者は救われる」という言葉は、地上のすべての国民・民族に福音が届けられるという世界宣教の偉業を担うにあたり、疲れず歩み続け、ついには信仰の競走をやり遂げる者に与えられる祝福の約束なのである。 こうした文脈の中で張ダビデ牧師は、終末論的な使命を明確に掴み取り、教会がどのように準備され、建て上げられるべきかを具体的に提示する。彼は特に「オリベット・ディスコース(Olivet Discourse)」――マタイ24~25章、マルコ13章、ルカ21章などにおけるイエスの終末説教――を非常に重視している。そのため、自身の宣教共同体や教育機関に「オリベット(Olivet)」という名称を冠している。イエスがオリーブ山(オリベ山)で終末の兆候や世の終わりに起こること、そして信じる者がいかに目を覚ましているべきかを教えられたその言葉自体が、教会と信徒にとって本質的かつ最終的な命令であるからだ。ローマ書9章が語る「残された者」の精神も、このオリベット・ディスコースの核心とつながり、終末論的に教会がどのような姿勢を取るべきかを教えてくれる。 救済論が正しく立っていなければ、終末論も誤りやすい。救済論がキリストの恵みと血潮の価値を弱めるなら、終末論は異端的終末論や、人間の功績や策略に満ちた倒錯した姿になりがちだ。その反面、救済論においてすでに十字架の血によって私たちは全面的な恵みにより救われたことを明確につかんでいる人であれば、終末論はなおさら「残された者」の精神をもって恵みを守りつつ、同時に世界へ福音を伝えていく躍動的な過程として理解される。張ダビデ牧師はローマ書9章と11章を共に学びながら、「神が残しておかれた種が、ついには新しい歴史を始める」という約束をしっかりつかむようにと強調する。だからこそ、どんな時代的・社会的混乱が襲おうとも、教会の内には必ず「種のトウモロコシ」のような人々がおり、彼らこそが福音の純度を守り、神の国のために献身する「残された者」となるのだ、と彼は説いている。 ローマ書9章後半が提示する核心は「イスラエルの子孫が海辺の砂のように多くても、残された者だけが救われる」という点であり、この「残された者」こそが「恵みによる選びによって神に握られた者」である(ローマ11:5)。私たちがこの恵みによって救いを得たように、最後までその恵みを固く握り、福音宣教と聖潔な生活を通して世の光となることが、終末論的な教会の姿勢である。このメッセージは、張ダビデ牧師が長年にわたり説教や著作を通じて強調してきたものであり、キリスト論・救済論が確立された後には、必ず正しい終末論の理解と実践が必要だと説いてきた文脈とも一致している。 2. 残された者のアイデンティティと使命 それでは具体的に、「残された者」として生きる信徒が志向すべき生き方や信仰姿勢とは何か。張ダビデ牧師はこれを大きく二つの側面で整理し提示している。第一に、「残された者は自らのアイデンティティを明確に認識すべきである」。第二に、「残された者は救いの種を守り、次世代と諸国へそれを伝えていくべきである」。この二つの側面こそが終末論的な教会の重要な柱であり、ローマ書9章と11章が語ることとも正確に合致する。 第一に、自らのアイデンティティの明確な認識とは、「私たちは恵みによって選ばれた者であり、神の救いの御業のために残された者だ」という意識を持つことを指す。これは決して高慢や優越感に陥ることではない。パウロがローマ書9章と11章で繰り返し強調しているのは、この選びが「行い」に基づくのではなく、「神の憐れみと慈しみ」によるという事実である。つまり、「自分が優れているから残された者になった」のではなく、「神が恵みによって残してくださったからこそ、私はここにいる」という悟りが必要なのだ。ゆえに残された者としてのアイデンティティを持つ信徒は同時に「へりくだる」べきであり、常に自分を振り返りながら「誰もが恵みから外れれば倒れ得る」という警戒心を持たねばならない。 張ダビデ牧師は、現代の教会が直面している様々な混乱――たとえば教会指導者の道徳的失敗や神学的な分裂、伝統的教団と改革運動の衝突など――に言及しつつ、「最終的に生き残るのは、ただ『恵みに捕らえられた人』と『真の福音に立つ人』だけだろう」と語る。しかしここでいう「生き残る」とは、他者を非難や攻撃によって排除することで達成されるのではなく、あくまでも神の御言葉と福音の中心へ立ち返ろうとする霊的な動きの中で、自ずと顕在化する現象だという。誰が真に福音を握っているのか、誰が十字架と復活の力を本当に頼りとしているのか、そして誰が最後まで耐え忍びつつ宣教と愛を実践するのかによって、「残された者」とそうでない者が分けられるのだ。 アイデンティティを明確に認識することは、キリスト者としての聖なる責任感を伴う。なぜなら「残された者」となることは、単に「自分が救われた」という安心感で終わるのではなく、教会共同体や諸国民に対する使命を全うしなければならないことを意味するからだ。私たちは、一世代で終わってしまう存在ではなく、次の世代と全世界のために聖なる種を託された者である。だからこそパウロはローマ書9章、10章、そして11章にわたって、イスラエルの例を挙げつつ「福音を聞かなければどうして信じられようか。信じなければどうして救われようか」と嘆き(ローマ10:14以下)、最終的に福音を宣べ伝える「残された者」の役割がいかに切実で重要かを力説している。 第二に、残された者は救いの種を守り、次世代と諸国に伝えるべきである。終末論でよく生じる誤解は、「どうせ世はもうすぐ終わるのだから、私たちはただ信仰を守って隠れていればよい」というような逃避主義的・宿命論的な態度である。しかしイエスの教えやパウロの書簡を詳しく見ると、いかなる場合でも教会が世に対して福音を証しする使命を放棄したり立ち止まったりしてよいとは書かれていない。福音宣教と霊的覚醒、そして愛の実践は、終末が近づくほどさらに必要になる。むしろ終末が迫るほど、教会がその種を守りながら諸国に広める責任は増大する。 張ダビデ牧師は自身の牧会経験と宣教活動の中で、世界のさまざまな地域を巡って福音を伝える過程で、「聖なる種」がどんな極限状況にあっても維持され、継承されていく光景を何度も目の当たりにしてきたという。たとえば共産主義国家やイスラム圏、あるいは宗教的迫害の厳しい地域においても、地下教会や小規模の信仰共同体が命がけで礼拝を捧げ、福音を伝えてきた。その姿は旧約の残された者、新約の初代教会の信徒たちと何ら変わらず、まさにローマ書が語る「恵みによって選ばれた者たち」の姿を映し出していた。彼らは決して大きな教勢や物質的なサポートを誇りにしていたわけではなく、「ただイエスの血と御言葉」に対する徹底した信頼で支えられていたのである。これこそ残された者が種を守る具体的な手本なのだと、張ダビデ牧師は語る。 このように種を守るということは、単に個人的な信仰告白にとどまらない。教会共同体の礼拝や聖餐、洗礼の執行、さらに御言葉の教育や宣教活動などが、種を守り伝えるための通路となる。さらに張ダビデ牧師は、教育機関、特に神学校やキリスト教大学が「残された者」を育て、種を次世代に手渡す中枢的役割を担うと考えていた。そのため彼が「オリベット(Olivet)」という名を冠して複数の教育機関や神学校、大学を設立したのも、その名称自体が「主の終末論的説教(オリベット・ディスコース)を継承し、実践する神学教育」を強調するためであった。世の文化や知識に染まりやすい時代に、「聖書へ戻る教育」を通して「残された者」を起こそうとする狙いだったのである。 「残された者は結局、歴史を生かすのだ」というのが、張ダビデ牧師がローマ書9章と11章を解釈しながら繰り返し提示してきた核心的結論である。ソドムとゴモラが滅びる際、義人が十人いれば滅びを免れただろうという創世記の記述が示すように、神はいつも歴史を破滅へ追いやるのではなく、義を求める者がいれば、彼らによって救いの道を開かれる。イスラエルの歴史が滅亡寸前に置かれた瞬間ごとに、「残された者」が再び復興と回復の出発点になった。そして新約の教会史においても、各地に残されていた者たちが福音を守り、中世の暗闇のような時代にも福音の火種が絶えず、改革者たちを立ち上がらせる原動力となった。 ローマ書9章はまさにこの点を思い起こさせ、キリスト者たちに「現在の状況がどれほど暗く見えても、神が主導される救いのドラマは決して止まらない」という希望を与えてくれる。「もし万軍の主が私たちに種を残しておかれなかったなら、私たちはソドムのようになり、ゴモラのようになっていたであろう」(ローマ9:29)という御言葉が、それを端的に示している。張ダビデ牧師は、この御言葉を現実に当てはめて、「今日、教会がどれほどみっともない姿をさらしていても、その内には依然として残された者が存在し、神は彼らを通して教会を再び立ち上げ、福音を全世界へ広められるのだ」と力説する。 残された者は、自分たちだけの孤立した共同体を築いたり、自分たちが満足するだけの信仰に陥ったりするのではなく、必ず「世を救う」方向へと進むという点にも注目すべきである。なぜなら、神は歴史の中でご自身の教会を招かれる際、単に教会を教会のままだけで存在させるのではなく、常に「あなたがたは世の光、地の塩となれ」という使命を委ねてこられたからである。その光と塩の役割を担う過程こそが、終末論的にさらに大きな患難や迫害の前で「残された者」が試される場面にもなる。張ダビデ牧師は「この使命から退かない者たちが最後まで耐え忍び、その耐え忍ぶ姿が逆説的に世を生かし、回復させる通路となる」と説明する。 ローマ書9章27節から29節が語るように、イスラエルの子孫がいかに多くとも、残される者だけが救われ、まさにその残された者を通じてソドムとゴモラのように完全に滅びる可能性もあった歴史が新しく開かれていくというメッセージは、今日の教会にもそのまま適用される。この御言葉は単なる旧約の歴史的記録ではなく、終末論的な展望まで含む、教会と信徒に対する警告であり慰めであり希望でもある。そして張ダビデ牧師が繰り返し強調してきたように、救済論が揺るぎなくなるほど、終末論も健全になり、終末論が明確になるほど、教会のアイデンティティと使命が一段と鮮明になる。私たちは「恵みによる選びに従って残された者」(ローマ11:5)であることを忘れず、同時にその恵みの通路となって世に福音を播き、愛を実践し、最後まで信仰を守り抜く生き方を歩むべきなのである。 このすべての過程を通して、歴史は神が定めた目的地へと徐々に進んでいく。一つの世代が去り、次の世代が来ようとも、地は永遠にあり、その地上には救われるべき人々と救いの種を伝えるべき人々がまだ残されている。私たちはその一部として招かれているのであり、それは私たちの力ではなく全的に神の恵みなのだ。ゆえに張ダビデ牧師の言うように、「残された者のアイデンティティ」は終末の時代を生きる教会と信徒にとって最も重要なメッセージの一つである。救済論の確信を抱き、終末論的ビジョンをしっかり掴むとき、私たちはソドムとゴモラのようになるかもしれなかった状況の中で、新たな歴史と回復への道を切り開く「聖なる種」となることができる。その使命の前で、日々新たに目を覚まして備え、恵みに感謝しつつ世へと踏み出していく――それこそがローマ書9章から11章に込められた大いなる流れであり、張ダビデ牧師が信徒たちに繰り返し教えている中心的な教えなのである。 www.davidjang.org
-
Pastor David Jang – Romans 9 and the Remnant
1. Beyond Soteriology to Eschatology Romans 9 occupies a very significant position as a turning point where eschatology (where is history headed, and how should Christians live in the final days?) is dealt with in earnest, along with Christology (Who is Christ?) and soteriology (How is a sinner made righteous and saved?). In particular, Pastor…
-
Pastor David Jang – Romanos 9 y el Remanente
1. De la doctrina de la salvación a la escatología El capítulo 9 de Romanos reviste una importancia extraordinaria porque, junto con la cristología (¿Quién es Cristo?) y la soteriología (¿Cómo se justifica el pecador y alcanza la salvación?), aborda de manera directa la escatología (¿Hacia dónde se dirige la historia?, ¿Cómo deben vivir los…
-
장재형목사 – 로마서 9장과 남은 자
1. 구원론을 넘어 종말론으로 로마서 9장은 기독론(그리스도는 누구신가), 구원론(죄인이 어떻게 의롭게 되어 구원에 이르는가)과 더불어 종말론(역사는 어디로 흘러가는가, 그리스도인은 최후에 어떻게 살아야 하는가)을 본격적으로 다루는 분기점이라는 점에서 매우 중요한 위치에 놓여 있다. 특히 장재형(장다윗)목사는 이 로마서 9장을 해설하면서, 여기서부터 11장까지 이어지는 본문이 단순히 학문적인 성경 해석이 아니라, 실질적으로 “구원받은 자들이 곧 어떻게 살아야 하는가”를 보여주는 구체적이고 실제적인 메시지라고 강조한다. 그리스도인은 이미 로마서 1장에서 8장에 이르는 구원론의 핵심을 받았고, ‘오직…
-
David Jang – Le Royaume de Dieu
Ⅰ. Le Royaume de Dieu vu à travers la christologie, la sotériologie et l’eschatologie Le pasteur David Jang met l’accent sur l’histoire de l’Église et sur les vérités fondamentales de la Bible en soulignant la manière dont les trois doctrines que sont la christologie, la sotériologie et l’eschatologie sont étroitement liées et conduisent finalement au…